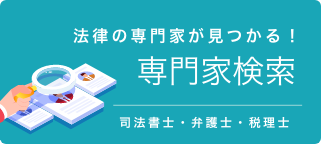相続全般の知識・手続き・相談
換価分割とは?不動産が売れない場合やトラブルについて徹底解説!

目次
相続における遺産分割の方法にはいくつか種類があります。その中でも「換価分割」は、不動産など分割が難しい場合に利用される方法です。土地や建物は簡単に分けられないため、換価分割がしばしば選択されます。本記事では、換価分割の基本的な仕組みから手続きの流れ、税金との関係、不動産が売れない場合の代替策や裁判所の関与、さらにトラブル事例までを詳しく解説します。
換価分割とは?読み方と基本的な仕組み
相続財産には、預金や株式のように簡単に分けられるものと、不動産や事業用資産のように分けにくいものがあります。後者の場合に有効な方法が換価分割です。
「換価分割」の読み方
「換価分割」とは「かんかぶんかつ」と読みます。法律や相続実務でよく登場する用語です。相続人同士で話し合いをする際にも、この用語を理解しておくことが重要です。
換価分割の定義と概要
換価分割とは、相続財産を一旦売却して現金化し、その代金を相続人間で分け合う方法です。例えば、不動産が遺産に含まれている場合、土地や建物をそのまま分割することは困難です。
そのため、売却して得た代金を各相続人の法定相続分や協議による割合に応じて分配します。
他の遺産分割方法(現物分割・代償分割)との違い
現物分割は相続財産をそのまま分ける方法で、土地を区画ごとに分けたり、預金を金額で割り振ったりするものです。
代償分割は特定の相続人が不動産などを取得し、他の相続人へ金銭を支払って公平性を保つ方法です。換価分割はこれらと異なり、一旦売却して現金に換える点に特徴があり、現金にすることで分配がしやすくなるというメリットがあります。
換価分割の手続きの流れ
換価分割を行うには、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、合意形成を図ることが必要です。この協議では、売却する不動産や財産の範囲、売却価格の目安、分配の割合、税金や諸費用の負担方法などを細かく話し合って取り決めます。
そのうえで不動産であれば不動産会社に依頼して売却活動を進め、買主が決まったら売買契約を締結します。契約締結後には、代金の受け渡しが行われ、売却代金は相続人間で取り決めた割合に従って分配されます。
遺産分割協議書を作成し、売却に伴う登記の抹消や所有権移転の手続きも必要です。加えて、売却までの間に発生する固定資産税や管理費、仲介手数料の負担についても協議内容に明記しておくと、後のトラブル防止につながります。
手続きには、不動産会社や司法書士の協力が不可欠であり、実務的には税理士や弁護士などの専門家に依頼して全体をサポートしてもらうケースが多いです。
換価分割と税金の関係
換価分割では税金の扱いが大きなポイントになります。譲渡所得税と相続税の関係を理解しておかないと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
譲渡所得税の発生について
相続によって取得した不動産を売却した場合、その売却益に譲渡所得税がかかる可能性があります。取得費や譲渡費用を控除したうえで利益が出れば課税対象となり、確定申告が必要になります。
売却時期や不動産の種類によって税率が変動するため、シミュレーションが必要です。相続税を納めた場合には「取得費加算の特例」が使える場合もあり、これを適用することで譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。
制度を正しく理解しておくことが、後々の税負担を大きく減らす鍵となります。そのため、早めに税理士に相談し、売却のタイミングや申告方法を確認しておくことが望ましいです。
確定申告に必要な書類(登記事項証明書、売買契約書、領収書など)を事前に整理しておけば、手続きがスムーズです。
譲渡所得は誰が払うのか?
譲渡所得税は、売却の名義人に課税されます。実際には売却益を相続人全員で分けるため、税負担の割合を事前に話し合っておかないと不公平が生じます。
協議書に負担割合を明記しておくと安心です。さらに、売却によって得られる現金の使い道(相続税の支払い、葬儀費用、生活資金など)をあらかじめ共有しておくと、税金支払いを巡るトラブルを避けやすくなります。
相続税との関係
換価分割を行っても、相続税の課税対象となる財産評価は変わりません。相続税は相続開始時点での評価額に基づいて計算されるため、売却価格が高くても低くても相続税には直接影響しません。
ただし、売却価格と評価額に差がある場合には相続人の納得感に影響し、心理的な不公平感を招くこともあります。この点を誤解していると、後で税負担を巡るトラブルが起こるため注意が必要です。
専門家のアドバイスを受け、評価額と市場価格の違いを丁寧に説明しておくことで、家族間の不信感を減らすことにつながります。
換価分割で不動産が売れない場合
換価分割は理論上はスムーズですが、現実には不動産が売れないという問題に直面することがあります。そのような場合のリスクや代替策を見ていきましょう。
売れない時に起こりやすい問題
売却が長引くと、相続人の間で現金分割が進まず、不満や対立が生じやすくなります。さらに、不動産を保有している間は固定資産税や管理費が発生し、相続人がその負担を分担しなければなりません。
市場の状況によっては時間が経つほど不動産価格が下落する可能性もあるため、早期の対応が求められます。加えて、売却できない間は空き家の維持管理が必要となり、防犯や近隣への影響、老朽化による修繕リスクも高まります。放置すると資産価値が下がるだけでなく、家族間で責任を押し付け合う状況にもつながりかねません。
そのため、売却が難航した際の対応策をあらかじめ検討しておくことが非常に重要です。
不動産が売却できない場合の代替策
不動産が売れない場合には、いくつかの代替策があります。一つは代償分割に切り替える方法です。相続人の一人が不動産を引き継ぎ、他の相続人に代償金を支払うことで公平性を保ちます。
もう一つは不動産を賃貸に出し、家賃収入を分け合う方法です。長期的な収益を得られる反面、管理や修繕の負担が続く点には注意が必要です。
将来的に価格上昇が見込まれる場合には一定期間保有してから売却する選択肢もありますが、その間の費用負担や管理体制をしっかり整える必要があります。相続人の状況に合わせて、柔軟に判断することが求められます。
裁判所の関与や競売の可能性
相続人の合意が得られず、売却が困難な場合には家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。最終的に競売となるケースもあり、競売では市場価格より安く売却される可能性が高い点に注意が必要です。
競売に至ると、相続人が望む形での売却や分配が難しくなるため、できるだけ相続人同士で合意を形成し、競売を避けることが望ましいでしょう。裁判所を利用する前に専門家を交えて冷静に協議を行い、可能な限り任意売却を成立させる工夫が重要です。
換価分割におけるトラブル事例
換価分割は便利な方法ですが、実務上はトラブルも多く発生しています。ここでは代表的なトラブル事例を紹介します。
売却価格を巡る争い
相続人の中には、「できるだけ高く売却したい」という人と、「早く現金化して分けたい」という人がいます。この意見の対立が売却活動を停滞させることがあります。売却のタイミングや不動産市況の見通しを巡って意見が食い違う場合も多く、相続人の間で不信感が生まれることもあります。
こうした状況を避けるには、仲介業者や不動産鑑定士など第三者の意見を取り入れて適正価格を客観的に把握し、時間をかけて丁寧に話し合いを進めることが大切です。
必要に応じて専門家を交えた協議の場を設けることで、当事者同士では解決できない問題を整理できる可能性もあります。
税金の負担割合を巡るトラブル
譲渡所得税や仲介手数料、登記費用などを誰がどの割合で負担するかをめぐって争いになることがあります。相続人ごとの負担能力や立場の違いから不公平感が生まれやすく、トラブルに発展するケースもあります。
事前に遺産分割協議書で細かく取り決めておくことが予防策となりますが、実務では曖昧なまま進めてしまい、後から揉めることもあるため注意が必要です。税理士や司法書士といった専門家に相談して、明確なルールを作っておくと安心です。
相続人間での合意が得られないケース
相続人の中には、換価分割自体に反対する人もいます。その結果、協議が進まず不動産が売れない状態が長引くこともあります。感情的な対立や過去の人間関係のしこりが原因で、合意形成が困難になることも少なくありません。
この場合、家庭裁判所での調停を経て解決を図るケースもあります。その場合は、早めに専門家を交えた話し合いを行うことが重要です。
まとめ
換価分割は、不動産など分割しにくい財産を公平に分けるための有効な方法です。ただし、実際には売却が難航したり、税金や費用負担を巡ってトラブルが生じたりする可能性があります。
そのため、相続人全員で事前にしっかり話し合い、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。信頼できる専門家に相談し、不要なトラブルを避け、円滑に手続きを行っていきましょう。
不動産の売却・リフォームのことなら大希企画株式会社に相談!
1988年創業の地域密着型の不動産会社「大希企画株式会社」は、20,000件以上のリフォーム実績を誇ります。長年の経験を活かし、相続に伴う不動産の売却やリフォーム、さらに空き家活用の相談にも幅広く対応しています。
空き家を賃貸やリノベーションで再利用する提案も行い、地域の暮らしを支えてきました。地域社会とともに歩み続ける信頼される企業として、安心できるサポートを提供しています。
相続や不動産に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ大希企画株式会社にご相談ください。
詳しくはこちらからご確認ください。
https://www.daiki-planning88.co.jp/index.html
この記事の著者
-

-
運営スタッフ
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。