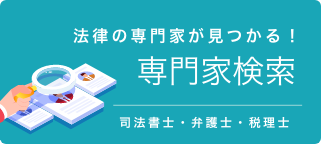相続
相続全般の知識・手続き・相談
推定相続人とは?「廃除」や法定相続人との違いについてわかりやすく解説!

目次
相続の準備や手続きを考える際、「推定相続人」という言葉を目にすることがあります。これは聞き慣れない方も多い用語ですが、実は相続の流れを理解する上で非常に重要な言葉です。本記事では、推定相続人の意味や範囲、法定相続人との違い、さらに廃除や遺留分など関連する制度について詳しく解説します。
推定相続人をわかりやすく解説
推定相続人という用語は、相続の知識がないと少し難しく感じられるかもしれません。しかし、その意味や位置づけを知ることで相続の全体像が見えやすくなります。この章では推定相続人の基本から順を追って解説します。
推定相続人の定義
推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となる人を指します。被相続人が生存している間における「将来の相続人候補」です。
ここで重要なのは、推定相続人はあくまで「現時点の見込み」に過ぎず、相続が実際に開始するまでは確定的な地位を持たないという点です。
法定相続人との関係
法定相続人は相続開始時に確定する相続人を指し、推定相続人は「現時点での候補者」という位置づけです。したがって、推定相続人は必ずしも最終的な相続人になるとは限りません。
例えば、推定相続人が相続開始前に死亡すれば、その人は相続人にならず、代襲相続の対象となる場合があります。このように、推定相続人と法定相続人の関係は流動的であり、事態の変化に応じて変動します。
推定相続人の範囲はどこまで?
推定相続人の範囲は、配偶者や子どもをはじめ、親、祖父母、兄弟姉妹にまで広がります。相続順位は民法で定められており、直系卑属(子や孫)が最優先され、次に直系尊属(親や祖父母)、さらにその次に兄弟姉妹が対象となります。
ここで大切なのは、順位ごとに相続権の強さや範囲が異なるという点です。例えば、子どもが複数いる場合には人数で均等に分割され、親や祖父母が相続する場合には、父母で2分の1の割合で分割します。
子がすでに死亡している場合には孫が代襲相続人として推定相続人となります。この代襲相続は、家系のつながりを守るための制度ともいえます。兄弟姉妹が相続人となる場合も、亡くなっている兄弟の子(甥や姪)が代襲することがあります。
但し、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は、民法では1代限りとされており、甥や姪の子には代襲は及びません。
配偶者は常に相続人となるため、どの順位の場合でも必ず推定相続人に含まれます。こうした複雑な順位構造を理解しておくことが、遺産分割協議や相続対策を行ううえで非常に大切です。
家族構成や状況によって誰が相続権を持つのかが変わるため、具体的なパターンを把握しておくと安心です。
推定相続人と法定相続人の違い
推定相続人と法定相続人は似ているようで実際には大きな違いがあります。両者の違いを理解することは、遺産分割の際の誤解やトラブルを防ぐために非常に重要です。
「推定」と「法定」の意味の違い
推定相続人は「相続開始前の見込み」、法定相続人は「相続開始後に確定する人」です。推定は暫定的な性質を持ち、法定は最終的に効力を持つ点が異なります。
例えば、推定相続人は、被相続人の意思表示や裁判所の判断によって廃除されることもありますが、法定相続人は相続開始の瞬間に確定し、法的権利を行使できる存在ともいえます。
実際の相続開始時にどう変わるか
推定相続人であっても、被相続人より先に死亡したり、廃除や相続放棄をした場合には相続人になれません。
逆に、当初は推定相続人でなかった人が、順位の変動や他の相続人の死亡などにより最終的に法定相続人となる場合もあります。この点は誤解されやすいため、相続計画を立てる際には「推定」と「法定」の違いを正確に理解しておく必要があります。
推定相続人の廃除について
廃除は相続制度の中でも特殊な手続きで、推定相続人に深刻な影響を与えます。どのような場合に廃除が行われるのかを理解することが相続トラブル防止につながります。
廃除とは何か
廃除とは、推定相続人が被相続人に対して著しい非行を行った場合などに、裁判所の判断で相続権を失わせる制度です。これは、被相続人の意思を最大限に尊重する制度であり、家庭裁判所の関与によって公平性が確保されています。
通常の相続の流れで相続権を持つ人であっても、この廃除制度によって権利を完全に失うことになるため、非常に強力かつ特殊な制度といえます。廃除の対象となる行為や手続きについて理解しておくことは、将来の相続トラブルを未然に防ぐ上で欠かせません。
廃除が認められる理由
虐待や重大な侮辱、著しい非行が、廃除が認められる代表的な理由です。例えば、被相続人に対して暴力をふるったり、日常的に人格を否定するような発言を繰り返した場合などが典型的です。
このような行為は家族関係を著しく損ない、相続の公正性を害するため、廃除が認められることになります。
金銭的に大きな迷惑をかける行為や、長期間にわたり被相続人を放置して扶養義務を果たさなかった場合なども、廃除の対象になる可能性があります。廃除が認められるには明確な理由が必要であり、被相続人の感情だけではなく裁判所が客観的に判断する点が特徴です。
廃除の手続きの流れ
被相続人が家庭裁判所に請求し、裁判所の審判によって認められます。遺言書で「相続人を廃除する」旨を記載することも可能です。遺言書で廃除を定めた場合には、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に確認を求める流れとなります。
このように、廃除には生前の手続きと遺言による手続きの2つの方法が存在します。さらに、廃除が認められるまでには証拠や事実の提示が必要であり、場合によっては証人の供述や医療記録などが重要な判断材料となることもあります。
廃除された場合の影響
廃除が行われた場合には遺産分割の割合が他の相続人に再配分されるため、残された家族の間で財産の分け方が大きく変わることになります。その結果、予期せぬ相続税負担や資産管理の問題が生じることもあり得ます。
このため、廃除制度は感情的な側面だけでなく、経済的・法律的な側面を踏まえて検討することが重要です。
推定相続人と遺留分の関係
遺留分は推定相続人にとって強い権利を持つ制度であり、遺言による財産配分と密接に関わっています。この章では、遺留分の基本的な仕組みと推定相続人の立場を解説します。
遺留分とは何か
遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の相続分のことです。被相続人が遺言によって自由に財産を分配できる一方で、家族関係の安定を守るために、一定の範囲の相続人には最低限の取り分が保障されています。
これは、民法によって厳密に定められており、遺言によっても奪うことができない権利です。例えば、配偶者や子どもは生活基盤を確保するために必ず一定割合を請求できる仕組みが用意されています。
このため、遺留分は「家族の最低限の生活を守る盾」ともいえる存在です。
推定相続人が持つ遺留分の割合
子どもや配偶者には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。例えば、子どもが2人いる場合には、遺産の2分の1が遺留分の対象となり、それを2人で分ける形となります。
親が相続人となる場合には3分の1が遺留分の対象となるなど、相続人の組み合わせによって割合が変化します。
兄弟姉の遺留分が認められない点には、注意が必要です。
遺留分侵害額請求との関係
遺言によって推定相続人の取り分が大幅に減らされても、遺留分を侵害された場合には「遺留分侵害額請求」が可能です。遺留分侵害額請求により、不当な遺産配分が是正され、相続人間の公平が保たれます。
実務では、遺留分侵害額請求は相続トラブルの中でも頻繁に問題となる重要な制度です。例えば、被相続人が全財産を特定の相続人に与える旨の遺言を残しても、他の相続人は遺留分を請求することによって最低限の権利を守ることができます。
遺留分の請求は金銭で行うのが原則であるため、不動産の共有化など複雑な問題を避けられるという実務的な利点もあります。請求には期限があり、相続開始や遺留分侵害を知った時点から1年以内に行う必要があるため、迅速な対応が求められます。
推定相続人に兄弟姉妹が含まれる場合
相続順位の変動によって、兄弟姉妹が推定相続人となるケースもあります。
兄弟が推定相続人になる条件
被相続人に配偶者や子ども、親がいない場合は、兄弟姉妹が推定相続人となります。また、兄弟姉妹のうち既に死亡している者がいる場合には、その子ども(甥や姪)が代襲相続人として相続権を持ちます。
他の相続人との順位関係
直系卑属・直系尊属がいないときに、兄弟姉妹が相続権を持ちます。ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で完全に排除されることもあり得ます。この点を理解しておかないと、相続開始後に思わぬ不公平感が生じることがあるため注意が必要です。
まとめ
推定相続人とは「将来相続人になる可能性のある人」を意味し、法定相続人とは異なります。廃除や遺留分といった制度を理解することで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
不動産や金融資産を多く保有する家庭では、推定相続人の範囲や権利を事前に把握することが大切といえます。
不動産の売却・リフォームのことなら大希企画株式会社に相談!
1988年創業の地域に根付いた不動産会社「大希企画株式会社」は、20,000件以上のリフォーム実績を誇ります。長年にわたり地域社会に貢献し、相続に伴う不動産売却や活用にも数多く対応してきました。
空き家利用プロジェクトでは地域の活性化に寄与しており、相談者の多様なニーズに応えてきた実績があります。相続後に生じる不動産管理やリフォームの課題についても、専門スタッフが丁寧に対応いたします。
安心して任せられるパートナーとして、相続に関するお悩みや不動産活用をぜひ大希企画株式会社にご相談ください。
詳しくはこちらからご確認ください。
https://www.daiki-planning88.co.jp/index.html
この記事の著者
-

-
運営スタッフ
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。