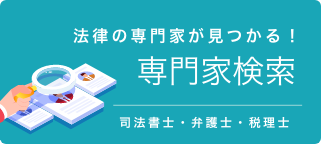相続全般の知識・手続き・相談
財産分割
包括受遺者とは?相続人との違いなどを分かりやすく解説

目次
相続に関する用語の中で「包括受遺者」という言葉を耳にすることがあります。しかし、相続人や受遺者との違いが分かりにくく、混乱する方も少なくありません。本記事では、包括受遺者の定義や読み方、相続人や特定受遺者との違い、遺産分割協議や税務関係との関わりをわかりやすく解説します。加えて、実際に包括受遺者になるための条件や、法律実務の中でどのように取り扱われるかも詳しく説明します。相続に備えて理解を深めることで、トラブルの回避や円滑な手続きにつながります。
包括受遺者とは?わかりやすく解説
包括受遺者という言葉は、相続関連の書類や専門家の説明の中で頻繁に登場しますが、その具体的な内容を理解している人は少ないです。
この章では、包括受遺者の基本的な意味や特徴について、法律的な観点と実務上のポイントを交えて解説します。
包括受遺者の定義
包括受遺者とは、遺言によって財産全体、または一定の割合で財産を承継することを指定された受遺者のことです。例えば「私の財産の2分の1をAに遺贈する」と記載された場合、Aは包括受遺者となります。
包括受遺者は、相続人と同様に相続財産全体に対して権利を持つ点が特徴です。さらに、相続債務についても相続人と同様に引き継ぐ必要があるため、受遺者は財産だけでなく債務承継のリスクも含めて理解しておくことが大切です。
読み方と基本的な意味
包括受遺者は「ほうかつじゅいしゃ」と読みます。法律用語として相続分野で使われる専門用語であり、判例や学説でも頻繁に登場します。
包括受遺者の立場を正しく理解することは、相続人や特定受遺者との関係を整理し、円滑に遺産分割を進めるうえで必要です。
「受遺者」との違い
受遺者には、「包括受遺者」と「特定受遺者」があります。特定受遺者は「この土地をBに与える」といった形で特定の財産を受け取る受遺者を指します。具体的には、預貯金や自宅、株式など個別の財産を単独で取得する立場などです。
一方、包括受遺者は財産全体に対して割合で承継するため、相続人に近い立場となります。そのため、承継する財産が包括的に及ぶことから、包括受遺者は相続人同様に債務も引き継ぐ義務を負います。
特定受遺者は、遺産分割協議に原則として参加できないのに対し、包括受遺者は協議に加わる権利を持つなど、法律上の位置づけや扱いにも違いが存在します。そのため、法的効果や税務上の取り扱いにも違いが生じ、実務においても大きな影響を及ぼすことになります。
包括受遺者なのか、特定受遺者なのかを理解することが重要といえます。
包括受遺者と特定受遺者の違い
包括受遺者と相続人はよく似た立場に見えますが、法律上の位置づけや権利の範囲には明確な違いがあります。
両者の違いを整理し、実際の相続手続きでどのように区別されるのかを分かりやすく説明します。
相続人と包括受遺者の権利の範囲
相続人は法律上当然に相続権を持ち、遺産の承継が発生します。一方、包括受遺者は遺言によって指定されるため、相続人と異なり法律上の当然の権利ではありません。ただし、包括受遺者は、相続人と同様に相続債務も承継する点が特徴です。
つまり、受け取る財産と同じく借金や未払い金などの債務も引き継ぐため、プラスの財産だけでなくマイナスの財産にも責任を負う立場になります。また、遺言の無効や取り消しによって効力を失うことがあります。
包括受遺者と特定受遺者との違い
特定受遺者は特定の財産のみを受け取るのに対し、包括受遺者は財産全体に対して権利を持ちます。そのため、包括受遺者は遺産分割協議に参加でき、他の相続人と同様に調整が必要となる場合があります。
相続債務の承継においても包括受遺者は責任を負う点で、特定受遺者とは大きく異なります。特定受遺者は原則として債務を負担しないため、同じ「受遺者」であっても立場は大きく異なるのです。
実際の相続においては、包括受遺者は相続人に近い立場として幅広い調整や協議に関わる一方、特定受遺者は限定された財産の受け取りに特化している点が大きな違いです。
包括受遺者になるには?
包括受遺者になるためには、被相続人が遺言書に「財産全体」または「一定の割合」を遺贈する旨を明記しておく必要があります。
親族以外の場合、遺言が有効に作成されていなければ包括受遺者としての効力は認められません。
したがって、公正証書遺言など確実な形式での作成が望まれます。また、遺言書の作成時には証人の立会いや公証人の関与など、形式的な要件を満たしているかを確認しておくことも重要です。
さらに、包括受遺者は遺言執行者の選任や家庭裁判所の関与によって手続きが進む場合もあるため、実務上の流れについても詳しく調べておきましょう。
場合によっては、他の相続人との調整や相続税申告の準備も同時に必要となるため、専門家の支援を受けて総合的に進めることが安心につながります。
包括受遺者と遺産分割協議
包括受遺者は、遺産分割協議に参加できます。相続人と同様に財産全体に関わる権利を持つため、分割協議における調整が必要です。
そもそも遺産分割協議とは、亡くなった人(被相続人)が残した財産を、相続人全員でどのように分けるかを話し合う手続きのことです。相続財産には不動産や預貯金、株式、車などさまざまなものが含まれ、誰がどれを相続するかを協議して決めます
実務の場面では、包括受遺者が他の相続人と利害が対立することもあり、協議の進行が難航する場合も少なくありません。
そのため、遺産分割協議書を作成する際には包括受遺者の署名や押印も必要となり、包括受遺者は形式的にも相続人と同じように扱われます。
場合によっては、家庭裁判所での調停や審判において包括受遺者が関与することもあり、包括受遺者の存在が協議全体に与える影響は非常に大きいといえます。
包括受遺者と税務関係
包括受遺者が財産を承継する際には、税務上の取り扱いが重要になります。ここでは相続税や所得税、さらには贈与税との違いについて整理し、税務処理の基礎を説明します。
相続税や所得税の関係
包括受遺者が受け取る財産は、相続税の課税対象となります。所得税ではなく相続税が適用されるため、贈与の場合とは異なる取り扱いになります。課税評価額や基礎控除を踏まえて申告が必要です。
不動産や株式など評価額が変動しやすい財産を含む場合には、適切な評価を行うことが重要になります。さらに、財産の評価方法によっては税額に大きな差が生じる可能性があるため、相続税評価額と市場価格の違いを理解しておきましょう。
包括受遺者は相続人と同様に相続税の連帯納付義務を負うことがあるため、他の相続人と連携して申告・納税を行う準備も求められます。
相続税と贈与税の違い
相続による承継は相続税、贈与による承継は贈与税の対象です。包括受遺者が遺言によって財産を取得する場合は相続税がかかります。この区別を理解しておくことで、税務上のトラブルを防ぐことができます。
場合によっては、二次相続や配偶者の税額軽減などにも関わるため、長期的な税務戦略を考える方もいます。贈与税は、相続税よりも税率が高くなるため、誤って贈与とみなされるような処理をしてしまうと、大きな負担が生じる可能性があります。
例えば、生前贈与と遺言による承継の扱いを混同すると、税務署から修正を求められる場合もあります。そのため、包括受遺者として遺言で財産を取得する場合は、必ず相続税として申告することを意識し、専門家に相談して確認を取ることが推奨されます。
包括受遺者と特定受遺者の事例比較
例えば「全財産の3分の1をCに遺贈する」と遺言に記載されている場合、Cは包括受遺者となります。この場合、Cは相続人と同様に遺産全体に対して権利を持つため、遺産分割協議にも参加する立場を持ち、債務の承継も伴います。
一方で「自宅の土地をDに遺贈する」と記載されている場合、Dは特定受遺者です。特定受遺者は指定された特定の財産のみを承継するため、包括受遺者のように遺産全体に関与することはありません。このように、遺言の内容によって立場や権利が大きく異なり、実際の相続手続きの中で果たす役割も変わってきます。
包括受遺者は、相続人と同じように相続税や債務の負担に関わる一方、遺産分割協議での調整役を担うこともあり、特定受遺者とは性質が大きく異なる点を理解しておく必要があります。
まとめ
包括受遺者は、遺言によって財産全体または一定割合を承継する受遺者であり、相続人に近い立場を持ちます。特定受遺者との違いや税務上の取り扱いを理解しておくことが重要です。
あわせて、包括受遺者は相続債務を承継する責任がある点や、遺産分割協議に参加する権利がある点も押さえておく必要があります。相続トラブルを防ぐためには、遺言書の内容を明確にしておくとともに、必要に応じて専門家に相談することが望まれます。
不動産の売却・リフォームのことなら大希企画株式会社に相談!
1988年創業の地域密着型の不動産会社「大希企画株式会社」は、20,000件以上のリフォーム実績を誇ります。長年の経験を活かし、相続に伴う不動産の売却やリフォーム、さらに空き家活用の相談にも幅広く対応しています。
空き家を賃貸やリノベーションで再利用する提案も行い、地域の暮らしを支えてきました。地域社会とともに歩み続ける信頼される企業として、安心できるサポートを提供しています。相続や不動産に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ大希企画株式会社にご相談ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
https://www.daiki-planning88.co.jp/index.html
この記事の著者
-

-
運営スタッフ
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。