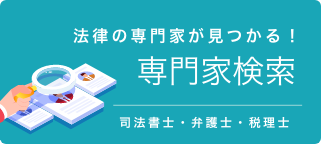相続
成年後見人
成年後見人の費用

目次
成年後見人の費用~どのくらいかかる?
成年後見人ってなに?
一言でいえば、本人の代わりに財産を管理する人です。自宅での生活が難しくなって施設に入るときなどは、必要に応じて施設との契約等入所手続きもやってくれます。
認知症になる人は年々増えており、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています(内閣府「平成29年高齢社会白書」より)。その予備軍も含めるとさらに多く、決して他人事とは言えません。
認知症になったからといって、すぐに成年後見開始の審判申立てが必要かというとそういうわけではありません。しかし、以下のような出来事に直面したとき、本人の意思能力がないことが問題となります。
- 本人の生活費が必要なので定期預金を解約したい
- 本人が施設に入ったので空き家になっている自宅を売却したい
- 身内が亡くなり本人を含めた相続人間で遺産分割協議をしたい
意思能力が求められる場面は、意外と身近に起こりうる出来事だと感じませんか?
他にも、アパート経営をしているなど管理財産が多い場合や、身の回りの世話をしてくれる身内がだれもいないような場合も、成年後見人が必要になることがあります。
ご注意いただきたいのは、一度成年後見が始まると、本人が完全に能力を回復するというような稀なケースを除いて、本人が亡くなるまでずっと続くということです。
成年後見人選任申立ての理由が不動産の売却のためであったとしても、売却が済んだからといって成年後見人が退任するわけではないのです。
日本人の平均寿命はどんどん伸びていますが、健康寿命はというと、平均寿命より10年前後短いといわれています。身体が健康な方は、認知症になってから10年以上お元気で過ごされることも珍しくない中で、成年後見人が必要な事態が1つくらい生じたとしてもなんら不思議はありません。
だれでもお世話になる可能性がある制度、それが成年後見なのです。
成年後見人の申立てとその費用
成年後見の申立てができる身内は、配偶者と4親等内の親族です。
【主な4親等内の親族】
親 祖父母 曾祖父母 子 孫 ひ孫 兄弟姉妹 おじ おば 甥姪 いとこ
配偶者の親 祖父母 曾祖父母 子 孫 ひ孫 配偶者の兄弟姉妹 おじ
おば 甥姪
それでは、成年後見開始の審判は、どのように申立てをしたらよいのでしょうか。
①成年後見申立て書類・費用の準備
まずは、必要な書類を集め、印紙・切手などを用意します。
| 内容 | 準備する書類等 | (書式等)入手先 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 福祉関係者に記入をお願いする | 診断書※1 記入済みの本人情報シート(原本)を医師へ渡す |
家庭裁判所・各医療機関 | 医療機関により異なるが数千円~1万円程度 |
| 申立人又は候補者が取得・収集する | 本人の戸籍謄本※1 | 本人の本籍地の役所 | 450円 |
| 本人の住民票(本籍・続柄入り、マイナンバーなし) (または戸籍の附票) ※1 |
本人の住所地の役所 (本人の本籍地の役所) |
300円前後 | |
| 本人の登記されていないことの証明書※1 | 全国の(地方)法務局本局戸籍課 (郵送の場合は東京法務局後見登録課) |
300円 | |
| 申立人の戸籍謄本※1 (本人との関係がわかるもの。本人と同じ戸籍であれば不要) |
申立人の本籍地の役所 | 450円 | |
| 後見人候補者の住民票(本籍・続柄入り、マイナンバーなし) (または戸籍の附票)※1 |
候補者住所地の役所 (候補者本籍地の役所) |
300円前後 | |
| 不動産の登記事項証明書 ※1 |
法務局 | 600円×不動産の数 | |
| 上記のほか財産・負債がわかる書類※2 | 本人又は管理者 | ||
| 収出がわかる書類※3 | 本人又は管理者 | ||
| 愛の手帳コピー(ある場合のみ) | 本人又は管理者 | ||
| 申立人又は候補者が記入する | 後見開始申立書 申立事情説明書 親族関係図 本人の財産目録 後見人等候補者事情説明書 収支予定表 |
家庭裁判所 (HPよりダウンロード可) |
|
| 本人の推定相続人に記入してもらう | 親族の意見書 | ||
| 申立てに必要な印紙・切手を準備する | 収入印紙(申立用) | 郵便局・法務局等 | 800円 |
| 収入印紙(登記用) | 郵便局・法務局等 | 2600円 | |
| 郵便切手(送達・送付費用) | 郵便局等 | 3000円~4000円程度 ※4 |
※1 申立日まで3ヶ月以内のもの
※2 預貯金通帳、保険証書、株式・投資信託等の資料、固定資産納税通知書等のコピー
負債の資料(住宅ローン残高証明書、金銭消費貸借契約書等)のコピー
※3 年金振込通知書、確定申告書、施設・病院の領収書等のコピー
※4 郵便切手代とその内訳については、各家庭裁判所により異なるため、事前に確認をすることをお勧めします。
②面接日の予約をとる
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に電話をし、面接日の予約をします。裁判所から、面接日当日持参するものについて指示があります。
③ ①の書類と費用を家庭裁判所に提出する
面接日までに裁判所が内容確認をするため、書類・費用の準備が調ったら速やかに管轄家庭裁判所に提出します。提出は、直接持参でも郵送でも構いません。「面接日の〇日前まで」というように提出期限が定められていることもありますので確認が必要です。
①の書類は、すべてコピーをとって手元に保管します。
④面接日に申立人及び成年後見人候補者が家庭裁判所に出向く
②で指示されたものと①のコピーを持って予約の時間に行きます。
後日、裁判所の判断で鑑定が必要になることがあります。診断書では後見相当か判断が難しい場合に、追加で医師に依頼するもので、10万円前後の費用がかかります。この手続きは省略されることもあります。
申立費用は原則申立人の負担となりますが、上記の費用のうち、収入印紙・郵便切手・鑑定費用は本人の財産からの支出とする旨を申立てることにより償還を求めることができます。
成年後見人選任申立ては、①のように必要となる書類等が多く、申立人がすべて行うとしたら時間的、労力的に負担になるかもしれません。その場合は、司法書士などが書類作成のお手伝いをすることができます。費用は事務所によって異なりますが、目安としては10万円~20万円程です。
申立てから選任の審判が下り、その登記がされるまで1~2か月かかります。不動産の売却の許可が必要な場合などはさらに期間が必要です。余裕を持って計画的に申立てをしましょう。
専門職後見人にかかる費用
本人の配偶者やお子様など身内の方が成年後見選任の申立てをする場合、多くが申立人自身かそのごく身近な方を候補者として申立てをしようと思うのではないでしょうか。
親族を候補者として申立てをした場合(却下の場合を除く)
- 親族がそのまま成年後見人に選任される
- 専門職成年後見人が選任される
- 親族が成年後見人に選任されるが監督人が付く
のいずれかになります。
この①~③のいずれとするかを決めるのは、申立てをした家庭裁判所です。
まずは、②の弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が成年後見人に選任された場合にかかる費用について見てみましょう。
通常は、1年間成年後見人としての務めを果たした後、裁判所に報酬付与の申立てをし認められて初めて報酬を受けることができます。そしてその額は、裁判所が決定します。
成年後見人の報酬は、基本報酬と付加報酬があります。
基本報酬は、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産)によって以下の価格が目安となります。
| (本人の管理財産の額) | (月額の報酬) |
|---|---|
| 1000万円以下 | 2万円 |
| 1000万円超~5000万円 | 3万円~4万円 |
| 5000万円超 | 5万円~6万円 |
付加報酬は、居住用不動産を家庭裁判所の許可を得て売却したり遺産分割調停を申立てたりして管理財産額を増加させた場合など、申立てにより裁判所の判断で追加として付与される報酬です。
いずれにしても報酬は、成年後見人からの申立てがあって初めて発生するもので、身内が成年後見人となる①の場合などは無報酬で行っても問題はありません。
では、身内が後見人となれる場合は成年後見制度を使いたいけれど、弁護士、司法書士などの第三者が選任されるのなら費用がかかるので申立てを取り下げたいという条件付きの申立て、あるいは、この候補者がだめならこちらの身内で、といった差替えなどは認められるでしょうか。
答えは、どちらもできません。
申立人が申立書類を裁判所に提出した時点で、公益性や本人保護といった見地から、申立人の取下げにより成年後見が行われない状況が相当ではないと考えられるため、裁判所の判断によらなければやめることはできなくなります。
成年後見人となる者についても、親族候補者の年齢や財産状況、本人の財産、その他さまざまな状況を考慮して裁判所の判断により選任され、この判断には不服申立てをすることはできません。
成年後見監督人が付く場合の費用
近年、親族後見人による本人の財産の不正な使い込みを防ぐため、ある程度流動資産を有している人の成年後見人には専門職の資格者を積極的に選任する流れでした。現在の親族後見人と専門職後見人の比率は、約30%が親族、約70%が専門職となっており、年々専門職後見人の割合が増す傾向にありました。
しかし、専門職後見人の報酬が大きく、費用負担を考えて申立てに二の足を踏む人も多いのは確かで、平成31年3月、最高裁判所は、これまでの「なるべく専門職から選任する」という方針から、「親族が望ましい」と方向転換していく見解を示しています。
そこで、成年後見人には親族候補者が選任されるけれども、専門職の成年後見監督人が付くというケースが今後増えていくことが考えられます。
これが、前出の「③親族が成年後見人に選任されるが監督人が付く」場合に当たります。
この成年後見監督人は、成年後見人の最初の後見事務である財産の調査及び財産目録の作成から立ち会い、以後必要があるときはいつでもその報告を求め、財産目録の提出を請求し、後見事務や本人の財産の状況を調査することができます。
成年後見人が本人の代わりに不動産の売却など重大な行為を行うときは、成年後見監督人の同意を得なければなりません。
さらに成年後見人がその任務を怠ったり不正な行為をしたような場合は、成年後見監督人は家庭裁判所に成年後見人の解任の請求をする権限もあります。
このように、成年後見監督人は成年後見人のお目付け役で、成年後見監督人が付いているかいないかは成年後見人にとって大きな意味があります。
さて、この成年後見監督人の報酬ですが、専門職が就く以上、無報酬というわけにはいきません。
基本報酬は、以下の金額が目安となります。
| (本人の管理財産の額) | (月額の報酬) |
|---|---|
| 5000万円以下 | 1万円~2万円 |
| 5000万円超 | 2万5000円~3万円 |
付加報酬は、専門職成年後見人の場合と同様です。
この金額を、専門職成年後見人の場合と比較して安いと思うかは難しいところです。
親族にとって、成年後見の事務は慣れていないことが多く、負担に感じる場合も少なくないかもしれません。ごく身近な親族が成年後見人となった場合でも、本人の財産を後見人自身のものとは明確に区別して管理し、すべての収支を監督人及び家庭裁判所にしっかりと説明できるようにしておかなければなりません。
成年後見人費用が払えない?~成年後見制度利用支援事業
では、必要があって成年後見人選任申立てをしなければならないのだが、本人が生活保護を受けているなど成年後見人選任申立費用や専門職成年後見人または成年後見監督人の報酬を支払う資力がない場合はどうすればいいでしょうか。
市区町村による「成年後見制度利用支援事業」の利用を検討してみることができます。
自治体により助成の範囲や条件等異なりますので、お住まいの地域の助成内容を事前に確認する必要がありますが、申立費用、報酬等の費用負担が困難な場合に、市区町村から必要な費用について補助を受けることができる制度です。
成年後見人等の報酬については、以下の金額を上限としている市区町村が多いようです。
在宅の場合 月額28,000円以内
施設入所の場合 月額18,000円以内
(これより少ない金額としている自治体もあります)
成年後見人等報酬の助成を、市区町村長申立ての場合に限っている自治体もありますので注意が必要です。
「市区町村長申立て」は、成年後見制度利用支援事業の一環で、身寄りがなく、成年後見人選任申立てをしてくれる親族が誰もいなかったり、あるいは親族がいても音信不通の状態にあるなど、必要があるのに身内から申立てができない場合に、本人が居住する地域の市区町村長が申立人となることができる制度です。
市区町村長による申立ての件数は、制度開始後年々増加し続けており、子からの申立てに次いで2番目に多い数となっている自治体もあります。
単身者が増え、市区町村長申立ての数は今後ますます増加するものとみられます。
おしまいに
成年後見人選任の申立て及びその報酬等成年後見人にかかる費用を中心に、成年後見制度をご紹介してきました。
祖父母が孫にお小遣いを渡したり、子供や孫との外食や旅行の費用も祖父母持ちというのは日常よく聞く話です。祖父母に孫の学費や習い事の月謝を払ってもらっているご家庭も多いことでしょう。何年にも渡って金銭的援助を続けており、祖父母自身がそれを望んでいることが明らかであったとしても、成年後見人がついたあとは今まで通りの援助を受けることはできなくなります。
本人のお金は基本的に本人とその扶養義務がある特定の家族の生活のためだけにしか使えず、それ以外に本人の財産を減らすような行為は、特別な事情で家庭裁判所の許可を得たような場合を除いて、できなくなります。
成年後年人は、あくまで本人の財産を守る(減らさない)ために存在するという立場上、ときとしてその相続人の利益とは相反する存在になってしまうこともあります。
このように書くと、親族から見て成年後見制度は使いづらくデメリットばかりのように感じてしまうかもしれませんね。
しかし、この制度がなかったとしたらどうなるでしょうか。
何も対策をとらずに認知症になってしまった場合、定期預金は凍結し、空き家を解消すべく自宅を売却したくても本人の意思確認ができないため売れない。そのうち介護費用が捻出できなくなって・・・困った事態になってもどうすることもできません。
成年後見人がいるからこそ、再び預貯金を動かし、不動産を売却できるようになるのです。
ですから、成年後見制度は、対策をとらないうちに認知症になって困った事態になったときの「最後の砦」と思っていただけると、携わる者としてはうれしい限りです。
そして、いまお元気なおじいちゃん、おばあちゃんは、ぜひご自分の財産の管理について対策をとっておいていただきたいと思います。
判断能力を失ってからはできませんが、お元気なうちに財産をまかせたい相手とその内容を自分で決めることができる「任意後見契約」を締結する方法があります。これは、公証役場で公正証書の形で契約する必要がありますが、法定の成年後見制度よりも本人の意思を反映した内容とすることができる点でメリットがあります。
また、比較的新しい仕組みとして「家族信託」を検討してみるのもよいでしょう。あくまで本人の代理人として財産管理をする任意後見とは異なり、財産権は本人に残しながら管理権を完全に信頼できる人(受託者)に移す仕組みです。不動産なども受託者名義となり、元気なうちから受託者に管理を任せて、認知症になっても関係なく継続することができる画期的な制度です。ただし、家族信託の内容とできるのはあくまで財産に関することのみで、身上監護は含まれませんので、必要であれば任意後見制度と組み合わせて契約するのも有効です。
どのような方法がそのご家族にもっとも適しているかの判断は非常に難しく、多面的に考える
必要がありますので、今のうちに、と思われる方はお早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
私は司法書士として不動産の売買に立ち会う中で、親の財産管理に悩まされているケースをたくさん目にしてきました。
元気なうちに自分の財産の道筋をつけておくことは、子供への最高のプレゼントとなるでしょう!
この記事の著者
-
-200x200.jpg)
-
司法書士
藤井 美穂
司法書士、家族信託専門士として活動しています不動産・商業登記全般、成年後見、家族信託、遺言書作成、遺産承継手続きに対応。特に財産承継に注力しています。
。司法書士として活動する前はTVのMC、レポーター、インタビューアーの経験があり、相手の気持に寄り添ったサポートに自信があります。
司法書士、家族信託専門士として活動しています不動産・商業登記全般、成年後見、家族信託、遺言書作成、遺産承継手続きに対応。特に財産承継に注力しています。
。司法書士として活動する前はTVのMC、レポーター、インタビューアーの経験があり、相手の気持に寄り添ったサポートに自信があります。