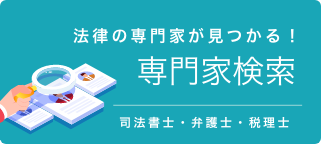生前贈与
生前贈与と遺留分の関係とは?相続トラブルを防ぐための対策をわかりやすく解説

目次
生前贈与と遺留分は、相続に関するトラブルでしばしば登場する重要なテーマです。家族への思いやりから行った贈与が、結果的に他の相続人の不満を生み、相続争いへと発展してしまうこともあります。その多くは、生前贈与と遺留分の関係を正しく理解していなかったことが原因です。この記事では、生前贈与と遺留分の基本から、影響する仕組み、注意点、トラブルを防ぐための具体的な対策までを詳しく解説します。相続を円満に進めたい方や、今のうちに備えたい方は、ぜひ参考にしてください。
生前贈与とは
生前贈与は、被相続人が生きている間に財産を譲る行為です。贈与を活用すれば、節税や財産の円滑な承継に役立ちますが、その扱い方を誤ると将来の相続に影響を与えることがあります。
生前贈与は、親や祖父母が自分の財産を子や孫に無償で譲る行為です。現金や預貯金、不動産、株式など、さまざまな財産が対象となります。たとえば、「相続のときに揉めないように、今のうちに分けておきたい」と考えて行う贈与は多く見られます。
さらに、贈与税の非課税制度(例えば110万円の基礎控除)を活用すれば、相続税対策としても効果的です。しかし、注意すべき点は、すべての贈与が相続人にとって公平なわけではないということです。特定の相続人にだけ多くの財産を渡すと、他の家族が不公平だと感じることがあります。
こうした不均衡が、後の遺留分侵害の主張やトラブルの火種になるのです。生前贈与は、感謝や愛情の表現である一方で、慎重な判断が求められる法的行為でもあります。
遺留分とは
遺留分は、相続人に対して法律で保障された最低限の取り分を指します。生前贈与や遺言で特定の人に財産が集中しても、一定の相続人にはこの遺留分が守られています。
遺留分が存在するのは、家族間の公平を保つためです。被相続人の自由な意思で財産を処分できるとはいえ、家族をまったく無視するような相続を認めてしまうと、生活が立ち行かなくなる相続人が出てしまうおそれがあります。
そのため、民法では一定の相続人に最低限の取り分を保障する仕組みを設けています。遺留分を持つのは、配偶者、子、または直系尊属(父母など)です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、遺留分の合計は法定相続分の半分となり、配偶者・子それぞれが一定の割合を主張できます。仮に遺言で「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、他の相続人は遺留分を請求することができます。
遺留分は、相続人間の公平を守るだけでなく、遺言や贈与の効力に制限をかける役割もあります。つまり、相続人の権利を保護する「安全装置」として機能しているのです。
生前贈与と遺留分の関係
生前贈与と遺留分の関係は非常に密接です。被相続人が生前に行った贈与の一部は、相続時に持ち戻して計算され、遺留分の侵害がないか確認されます。ここでは、その仕組みを具体的に見ていきましょう。
贈与と相続の境界
贈与と相続は本来別の行為ですが、相続に影響を及ぼす場合があります。それが「特別受益」と呼ばれる考え方です。被相続人が生前に特定の相続人に多くの財産を与えていた場合、それは「他の相続人よりも特別な利益を受けた」と判断され、相続時にその分を考慮して全体の分配を見直すことになります。
たとえば、長男に住宅資金として2000万円を贈与し、次男には何も贈与していなかった場合、相続時には長男の受けた金額を含めて相続財産を再計算します。これにより、他の相続人が不利益を被らないように調整されるのです。
この制度は、家族間の公平性を守るために設けられたものであり、意図せず不均衡が生まれてしまった場合でも、法的にバランスを取り戻せる仕組みとなっています。
贈与の時期と範囲のルール
遺留分の計算に含まれる贈与には期間制限があります。民法改正により、相続開始前の10年以内に行われた贈与は、遺留分算定の対象に含まれることが明確になりました。これを「10年ルール」といいます。
一方で、10年以上前の贈与は、原則として遺留分の対象外です。ただし、相続人に対して行われた贈与については、相続開始1年以内であればすべて対象に含まれる可能性があります。このルールにより、贈与のタイミングが非常に重要になりました。相続開始直前に行った贈与は、ほぼ確実に遺留分に影響します。
反対に、計画的に時間をかけて行う贈与であれば、相続発生時に問題とならないケースもあります。たとえば、親が子に毎年少しずつ贈与することで、税務面でも法的にもリスクを抑えることができます。こうした長期的な設計が、生前贈与を成功させるポイントです。
遺留分侵害額請求の仕組み
遺留分を侵害された相続人は、一定の手続きを経て金銭の支払いを求めることができます。これを「遺留分侵害額請求」といい、家族間の公平を取り戻すための制度です。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求は、他の相続人や贈与を受けた人に対して、不足分の金銭支払いを求める手続きです。たとえば、相続財産のうち生前贈与分を加味して計算した結果、自分の遺留分を下回っていると判明した場合、侵害された金額を請求できます。
2019年の法改正以前は、財産そのものの返還を求める「減殺請求」が認められていましたが、現在は金銭請求に一本化され、より実務的な運用が可能になりました。この制度によって、相続人間の感情的な対立をある程度緩和しつつ、権利を守ることができます。
財産の現物返還ではなく金銭清算で済むため、実際の生活への影響を最小限に抑えられる点が特徴です。
手続きと注意点
遺留分侵害額請求には時効があります。相続開始および侵害の事実を知った時から1年以内に請求しなければならず、また相続開始から10年が経過すると、請求する権利自体が消滅します。
この期限を過ぎると、どれだけ正当な理由があっても主張できません。そのため、相続が発生したら早めに贈与や遺言の内容を確認し、必要があれば専門家に相談することが重要です。請求はまず内容証明郵便などで相手に通知します。話し合いで解決できなければ、家庭裁判所での調停や訴訟に進む流れになります。
なお、遺留分侵害額請求は家族間の信頼関係に影響を与えることが多いため、冷静に事実を整理し、感情的な対立を避ける努力が必要です。
生前贈与を行う際の注意点
生前贈与は、円満な相続を目指すうえで非常に有効ですが、実行する際にはいくつかの落とし穴があります。ここでは、贈与を行う前に確認しておきたいポイントを解説します。
書面での記録を残す
贈与を行う際は、必ず書面で契約内容を残すことが重要です。贈与契約書を作成し、贈与の金額、日付、目的、署名を明記しておくことで、後に「それは借金ではないか」「返還の約束があったのではないか」といった争いを避けられます。
特に親子間の金銭のやり取りは曖昧になりやすく、証拠がなければ後に法的トラブルへ発展することもあります。小さな金額でも、記録を残しておくことが信頼関係を守る第一歩です。
他の相続人への配慮
生前贈与をするときは、他の相続人に対する説明や配慮が必要です。たとえば、長男に多く贈与した場合には、その理由を家族に伝えておくと良いでしょう。
特定の相続人だけが優遇されているように見えると、遺留分をめぐる不満が生まれやすくなります。家族全員が納得していれば、相続時に「なぜあの人だけ」といった感情的な問題が起きにくくなります。
税金面の確認
生前贈与には、贈与税がかかる可能性があります。年間110万円を超える贈与を行うと課税対象となり、申告が必要です。また、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の計算に加算されるため注意が必要です。
こうした税務上のルールを正しく理解せずに贈与を行うと、節税どころか余分な税負担を招くおそれがあります。専門家と相談し、贈与と相続を一体的に設計することが大切です。
遺留分トラブルを防ぐための対策
相続トラブルを防ぐためには、事前の備えが欠かせません。ここでは、生前の段階で実践できる効果的な対策を紹介します。
遺言書の作成
遺言書は、被相続人の意思を明確に残す最も有効な方法です。特に公正証書遺言は法的効力が高く、のちにトラブルになりにくいのでおすすめです。
遺言書に「なぜ特定の人に多く渡すのか」という理由を書き添えることで、他の相続人が納得しやすくなります。また、遺言書の内容と生前贈与の内容を整合させておくことで、相続時の混乱を防げます。
家族間の事前調整
生前のうちに、家族で財産の分配について話し合うことは、最も効果的な予防策です。相続の段階で初めて贈与の事実を知ると、感情的な反発が起こりやすくなります。定期的に家族会議を開き、資産の現状や考えを共有することで、相互理解を深められます。
こうした対話の積み重ねが、将来の相続を円満に進めるために必要です。
専門家への相談
生前贈与や遺留分に関する判断は複雑であり、法律、税金、不動産評価など多方面の知識が必要です。弁護士や税理士、司法書士に相談すれば、具体的なリスクを事前に把握し、適切な対応をとることができます。
特に不動産を贈与する場合は、登記や評価額の問題が絡むため、専門家の助言は重要です。独断で判断せず、第三者の視点を取り入れることで、安心して贈与を進められます。
生前贈与と遺留分を正しく理解して円満な相続を実現しよう
生前贈与は、家族への感謝を形にする手段ですが、その方法を誤ると遺留分侵害などのトラブルを招きかねません。贈与を行う際は、贈与契約書を作成して記録を残し、他の相続人への説明を怠らないことが大切です。
また、贈与税や相続税のルールを理解し、必要に応じて専門家に相談しましょう。遺言書を活用して意思を明確に示すことも、家族の信頼関係を保つ大きな助けになります。円満な相続を実現するためには、感情ではなく計画性と準備が重要といえます。
大希企画株式会社へのご案内
相続で取得した不動産や空き家の活用にお悩みの方は、地域密着の不動産会社「大希企画株式会社」に相談するのがおすすめです。リフォーム・リノベーション、不動産売却など幅広いサービスを提供しています。
相続した家をそのまま維持するか、リフォームして資産価値を高めるか、売却して現金化するかなど、状況に応じた最適な提案を受けられます。相続と不動産は切り離せない関係にあり、専門的な視点からアドバイスをもらうことで、安心して次の一歩を踏み出せます。詳しくは大希企画株式会社公式サイトをご覧ください。
この記事の著者
-

-
運営スタッフ
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。