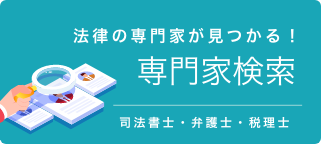不動産の活用・相続
国際相続とは?海外に資産があるときの手続きや注意点を徹底解説!

目次
海外に資産がある相続は、国内相続に比べて法律や税制が複雑であり、思わぬトラブルに発展することが多いです。本記事では、国際相続の基本的な流れや必要な手続き、注意すべきポイントを分かりやすく解説します。早めの準備により、安心して手続きを進めるようにしましょう。
国際相続とは?
国際相続とは、相続財産や相続人が国境をまたぐケースに適用される相続のことです。
国際相続では、相続税制度が国ごとに大きく異なり、場合によっては二重課税や権利関係の混乱が生じることもあります。
国内相続と比較すると、複数の国の法律や制度が絡み合うため、より複雑で慎重な対応が必要であり、情報収集や専門家の関与が欠かせません。
国際相続が発生する主なケース
国際相続は、海外の不動産や金融資産を所有している場合、相続人が外国籍または海外居住者である場合に発生します。また、国際結婚によって家族が複数の国にまたがっている場合、ビジネス活動を通じて海外に資産を持っている場合も対象です。
例えば、日本に住む外国人がアメリカに銀行口座を持ちつつ、ヨーロッパに不動産を所有している場合には、複数の国の制度を横断することになります。また、配偶者や子どもが外国籍を持っている場合には、相続権や税務の取り扱いが国ごとに異なるため、一層慎重な対応が必要です。
各国の課税ルールが同時に影響を及ぼすため、相続人同士の調整や現地の行政機関とのやり取りも必要です。結果として、多くの時間と労力が必要となり、早期の備えが重要です。
国際相続の基本的な流れ
国際相続の流れは、大きく五つの段階に整理できます。国際相続が適用される場合の基本的な流れを確認しましょう。
- 被相続人の死亡によって相続が開始する。
死亡が確認された時点で相続は発生し、その瞬間から国内外にある資産や負債が相続の対象となります。 - 国内外の財産や負債の調査を行い、資産を正確に把握する。
銀行口座や不動産、株式などの有無を明確にし、現地の登記機関や金融機関への照会を通じて資産の全体像を把握する必要があります。 - 国際私法や現地法に基づいて適用される法律を確認する。
被相続人の本国法が原則となりますが、資産のある国の法律が優先される場合もあり、複数の法律が絡み合うため専門的な判断が必要です。 - 必要な証明書や関連書類を国内外で収集し、相続人同士で協議を行う。
死亡証明書や戸籍謄本のほか、現地で公的に認められる書類を整えなければならず、翻訳や公証が必要となる場合もあります。そのうえで相続人間で協議し、公平な分割を進めることが重要です。 - 日本と海外の双方で必要となる税務申告を実施し、資産の管理や清算を進める。
二重課税を避けるための条約の確認が必要であり、最後まで慎重に進めることが求められます。
どこかで遅れや不備が生じると全体の進行に支障をきたします。国際相続では、国内だけの相続と比べて法的・実務的な注意点が多く存在します。そのため、手続きを滞りなく進めるためには、各段階での確認を怠らず、専門家の協力を得ながら計画的に取り組むことが必要です。
国際相続で必要な手続きの流れ
国際相続の手続きには、いくつか確認すべきことがあります。どのような手続きを行うべきかを解説します。
1.適用法の確認
国際相続では、どの国の法律が優先されるかが重要です。日本の「国際私法(法の適用に関する通則法)」では、被相続人の本国法を適用することが原則とされています。ただし、遺産が所在する国の法律が優先される場合もあるため、両国の法制度を照らし合わせて判断する必要があります。
適用法の確認を怠ると、手続きの進行が止まったり、相続人間での解釈の相違が生じたりするため、専門家の助言を受けながら進めることが望ましいといえます。
また、国によっては遺言の効力や相続権の範囲が日本と異なるため、事前に確認しておくことでトラブルの防止につながります。
2.海外資産の調査
海外資産の把握は、国内の相続以上に難易度が高いです。銀行口座や不動産、株式などは国ごとに確認方法や必要書類が異なります。現地の登記機関や金融機関に直接照会する必要があり、専門家を通じた調査を行うことで正確かつ効率的に進められます。
不動産は、現地法に基づいた権利証明が求められる場合が多く、書類の不備があると相続の実行が遅れる可能性があります。
3.税務申告
相続税に関しては、日本国内の居住状況や資産の所在によって課税範囲が異なります。海外資産がある場合には、日本と海外の双方で課税されるケースがあり、二重課税の問題が発生します。
その際には、外国税額控除の利用を検討し、税務上の負担を軽減する必要があります。税務申告は期限が設けられているため、準備を怠ると延滞税や加算税といった追加負担が生じます。
国際相続の注意点
国際相続を行う際には、いくつか注意点があります。どのような点に注意すべきかを確認しましょう。
二重課税
国際相続の最も大きなリスクのひとつは、同じ資産に対して日本と外国で相続税が課される二重課税です。控除制度を利用しなければ、不要な税負担が発生する可能性があります。たとえば、アメリカに不動産を所有し、日本に居住していた被相続人の場合、日本とアメリカの双方で相続税の対象となることがあります。
事前に二重課税防止条約の有無を確認し、適切に税務申告を行う必要があります。事前の確認と準備が欠かせないのはそのためです。
手続きの煩雑さ
各国で必要とされる書類や認証方法は異なります。例えば、現地法で求められる死亡証明や戸籍に相当する書類は、日本の書式ではそのまま認められないことがあり、追加で現地の認証手続きを経る必要があります。
スムーズに進めるには、現地の制度を理解する専門家の支援が必要であり、自己判断で進めると余計に時間がかかります。
相続人間のトラブル
海外在住の相続人との意思疎通は、時差や文化的背景の違いから難航することがあります。連絡不足が続けば、協議が長期化したり、不信感が募ってトラブルへ発展する恐れがあります。
メールや電話だけでは誤解が生じやすいため、専門家を交えた会議を行うことが有効です。定期的な連絡と透明性のある情報共有が求められるのは、こうしたリスクを最小限に抑えるためです。
国際相続をスムーズに進めるためのポイント
国際相続を円滑に進めるためには、いくつかの重要な準備があります。まず、国際相続に詳しい専門家へ早めに相談し、全体の流れを把握することが重要です。
次に、海外資産の内容を正確にリスト化し、関係する書類を整理しておきます。翻訳や公証の手続きは事前に準備を進め、遅延を防ぐことが効果的です。また、相続人同士の信頼関係を維持するために、定期的なコミュニケーションを行うことも必要です。
二重課税防止条約や現地の法律を確認し、余計な税負担を回避する工夫も必要です。
国際相続で無料相談はできる?
国際相続は、国内相続に比べて手続きが複雑なため、まずは無料相談を活用することが有効です。弁護士や司法書士、税理士の中には初回相談を無料で受け付けている事務所もあり、国際相続に特化したアドバイスを得られる場合があります。
市区町村や法テラスなどの公的機関でも、一定の範囲で無料相談が設けられているケースがあります。費用をかけずに専門家に相談することで、自分の状況に適した解決の方向性を見極めやすくなります。
無料相談では、手続きの全体像や必要となる書類の確認、想定される費用の概算なども聞くことができるため、実際に有料の依頼をする前の判断材料として役立ちます。短時間でも専門家に相談することで、自分では気づかなかったリスクを事前に把握できるのもよいでしょう。
国際相続を弁護士に相談するとどのくらいの費用?
国際相続を弁護士に相談する場合、費用は相談内容や事務所の方針によって異なります。初回相談は、無料または1時間あたり5,000円から1万円程度で設定されているケースが多いです。具体的な相続手続きの代理を依頼する場合には、着手金や報酬金が発生します。
相続財産の規模や複雑さによって費用は変動し、数十万円から数百万円に及ぶこともあります。海外資産が絡む場合には、翻訳や現地での登記手続き、外国の専門家との連携に伴う追加費用が必要となることが多く、全体の負担は国内相続に比べて大きくなる傾向があります。
依頼内容によっては、遺産分割協議のサポート、国際税務に関するアドバイス、海外での訴訟対応などが含まれるため、費用総額は大きく変動します。そのため、契約前に見積もりを詳細に確認し、追加料金の有無についても明確にしておくことが大切です。
不動産の売却・リフォームの依頼は、大希企画株式会社がおすすめ!
不動産の売却やリフォームを検討しているなら、大希企画株式会社がおすすめです。1988年の創業以来、地域密着の不動産会社として30年以上にわたり幅広い相談に応えてきました。
相続不動産の売却や空き家のリフォームなどを得意とし、施工実績は20,000件以上あります。戸建て・マンションどちらも豊富な経験があるため、不動産の売却・リフォームを検討している方は、ぜひ相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
まとめ
国際相続は、国内の相続に比べて税制の複雑さが増し、手続きにかかる時間も大きくなります。こうした状況を回避するには、早い段階から準備を整え、専門家の協力を得ることが必要です。トラブルを防ぎ円滑に進めるために、今から備えておくことが望まれます。
この記事の著者
-

-
運営スタッフ
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。