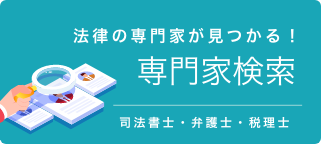相続
相続人
任意後見人とは

任意後見制度とは
原則として、判断能力に問題が生じておらず、自ら単独で各種契約を締結することが出来る段階において、「あらかじめ」判断能力が不十分な状況に陥ったときに備えて、自己の生活、療養看護、財産管理に関する事務を代理して執り行う任意後見人及びその権限を決めておく制度です。
任意後見制度の特色
任意後見制度に限らず、人に何かをお願いして、そのためにその人に代理権を与えるということは、皆様が日常的に行っていることかと思います。そのような行為に際して、裁判所や公証人が関与することは通常ありません。なぜなら、お願いをした人には、お願いをされた人を適切に監督できる能力があるという前提があるため、第三者の関与が必要ないからです。
他方、任意後見制度においてはいかがでしょうか?
本人の判断能力が不十分な状況に陥ったときから、任意後見人が本人を代理して各種行為を行うことになりますので、本人が任意後見人を適切に監督することは難しいということになります。
この問題を解消するため、まずは、任意後見契約の際、本人の意思確認や不当な内容が盛り込まれないように、公証人を関与させて、公正証書により契約することが定められています。
次に、実際に任意後見契約の効力を発生させるときにおいては、申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その後は本人に代わりその者に任意後見人を監督させることで、適切な後見事務を保証するという仕組みになっております。
更に、私のように公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属している者は、当該法人による監督も受けます。
最後に、任意後見契約を締結した場合は、公証人からの嘱託申請により法務局にその旨の登記がなされます。その後、任意後見監督人選任の申立てがなされれば、任意後見人等の情報が登記されます。
したがって、金融機関等に対して、法務局にて発行される登記事項証明書という公的な書面により、自らの代理権を証明することが出来ます。
任意後見人を依頼するメリット&デメリット
(メリット)
・後見人を自由に選べます。
→ 成年後見制度:候補者を立てられるに止まり、最終的な選任権限は家庭裁判所にあります。
・依頼する後見事務の内容を自由に選べます。居住用不動産の処分に関しても、家庭裁判所の許可無く行うことが出来ます。
→ 成年後見制度:居住用不動産の処分に関しては、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
・後見人の報酬を、無償を含め自由に設定できます。
→ 成年後見制度:後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。
(デメリット)
・任意後見監督人に関しては、候補者を推薦できるに止まり、最終的な選任権限は家庭裁判所にあります。
・任意後見監督人を選任されることで、家庭裁判所からの監督を受けることになります。
・任意後見監督人に対し、日頃の後見事務の内容を書面にまとめて、定期的に報告する義務があります。
・任意後見監督人に対し、報酬を支払う必要があります。
・成年後見制度と異なり、本人による法律行為への取消権や同意権はありません。
任意後見人の手続きにかかる費用の相場
事務所によって個々に報酬設定をしておりますが、任意後見契約書作成費用の目安としては、10万円から20万円ほどを想定していただければと思います。
別途、当該契約書を公正証書として作成するために、公証役場に対し、約3万円を支払う必要があります。
この記事の著者
-

-
司法書士
千北 正直
昭和52年出生 佐賀県出身
東京司法書士会 登録 第7446号
簡易裁判所訴訟代理 認定 第1601006号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 3111584
法テラス契約司法書士 東京法務局杉並出張所嘱託相談員
当事務所HPhttps://masanaochikita.wixsite.com/mysite
昭和52年出生 佐賀県出身
東京司法書士会 登録 第7446号
簡易裁判所訴訟代理 認定 第1601006号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 3111584
法テラス契約司法書士 東京法務局杉並出張所嘱託相談員
当事務所HPhttps://masanaochikita.wixsite.com/mysite