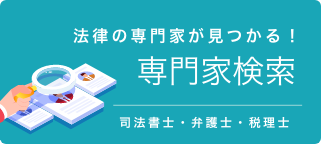相続全般の知識・手続き・相談
相続開始日の決まり方とは?トラブルを避けるための注意点を解説!

目次
相続が発生した際、確認すべき重要な日付が「相続の開始を知った日」です。相続開始日と相続の開始を知った日を正確に理解していないと、相続税の申告期限を逃したり、相続放棄の権利を失ってしまうなどのトラブルにつながる恐れがあります。不動産や金融資産を含む相続では、手続きが複雑になりやすいため、きちんと理解しましょう。
本記事では、相続開始日や相続開始を知った日の定義、トラブル事例などを具体的に解説し、安心して相続手続きを進めるためのポイントもあわせて紹介します。
相続開始日とは?

相続開始日とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した日を指します。一方、相続開始を知った日とは、言葉のとおり相続開始を知った日のことを指します。
どちらの日付が適用されるかは、後ほど詳しく解説しますが、相続を行う手続きにより異なります。
たとえば、被相続人が10月1日に亡くなってしまい、相続人が10月4日にその事実を知れば、相続開始を知った日は10月4日になります。つまり、この場合、相続税の申告・納付期限は、相続を知った日(10月4日)の翌日から10か月以内となります。
相続開始日が「死亡日」として記載されます。死亡日と実際の発見日が異なるケースや、災害・事故による死亡推定日が使われる場合もあるため、相続開始日について正確な理解を持つことが大切です。
相続の開始日(相続開始を知った日)が関係する主な手続き

相続開始を知った日を起点として、相続に関するさまざまな手続きが進行します。期限が決まっている相続税の申告や相続放棄などは、日付の認識違いによって大きなトラブルを招くことがあります。ここでは、相続関連の手続きを整理して解説します。
相続税の申告・納付期限(10か月以内)
相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付が必要です。期限を過ぎると延滞税が課され、余分な税負担が生じる可能性があります。相続財産に不動産が含まれる場合は、評価や売却準備に時間がかかるため、早めの対応が重要です。
加えて、税務署とのやりとりや資料収集にも一定の時間が必要です。納税資金をどう確保するか、物納や延納が可能かどうかも含めて、早期の税理士相談をおすすめします。
相続放棄・限定承認の申述期限(3か月以内)
自分のために相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述を行えば、相続放棄や限定承認が可能です。この熟慮期間を過ぎてしまうと、自動的に「単純承認」となり、プラスの財産だけでなく借金や負債もすべて引き継ぐことになります。
放棄や限定承認を検討している場合、遺産の全体像を短期間で把握する必要があります。遺品整理や通帳確認、不動産の権利関係調査などを迅速に進める体制を整えましょう。
相続開始日(被相続人の死亡日)の確認方法と必要書類
相続開始日(被相続人の死亡日)を把握するためには、公的な書類に記載された「死亡日」を確認する必要があります。戸籍や死亡診断書などは、手続きの根拠となるため、取得と確認を早めに進めることが重要です。
戸籍謄本
被相続人の除籍謄本などを取得することで、正式な死亡日を確認できます。
自治体によっては郵送請求やマイナンバーカードを用いたオンライン申請も可能です。事前に本籍地を確認し、戸籍取得に要する時間も考慮して準備を進めましょう。
死亡診断書の確認
医療機関が発行する死亡診断書にも死亡日が記載されています。保険金請求などには、この診断書が使用されるケースが多いです。
相続開始日に関する誤解と注意点

相続開始日については、意外にも多くの方が誤解をしている部分があります。発見日や届け日、知った日と混同したまま手続きを進めてしまうと、後々の手続きで問題が発生することも少なくありません。
発見日や死亡推定日、相続を知った日との混同に注意
遺体の発見日や死亡推定日は、ひとつの情報にすぎず、死亡日が相続税の基準日ではないため、なにを基準日としているかの確認が重要です。
相続税の期限は、相続を知った日の翌日から10か月以内であり、限定承認・相続放棄の期限は、相続を知ってから3か月以内と異なります。
死亡届の提出日=開始日ではない
死亡届の提出日と実際の死亡日が異なることがあります。たとえば、休日や深夜に死亡が確認された場合、届け出が翌日になることも珍しくありません。実際の死亡日を利用する場合は、届け日と混同しないよう注意が必要です。
相続時の実際のトラブル事例と防止策

実際に相続開始日をめぐって発生するトラブルがいくつかあります。ここでは代表的なケースを紹介しながら、それぞれの問題を未然に防ぐための対策を解説します。
申告期限を過ぎて延滞税が発生
申告期限を勘違いした結果、10か月の申告期限を逃し、相続税に延滞税が発生する場合があります。延滞税は税率が高く、納税額が大幅に膨らむ要因となるため、注意が必要です。
家族内でも情報共有が不十分な場合にこうしたミスが起こりやすいです。
したがって、相続開始日が確定した段階で、相続人全員で正確な日付を共有し、必要に応じて税理士などの専門家に相談しながら早期に対応を始めることが重要です。
相続放棄が無効とされるケース
相続放棄には、相続開始日を知った日から3か月以内という厳格な期限があります。この期間を過ぎた後に相続放棄を申述しても、家庭裁判所が受理しない可能性が高く、放棄は無効とされます。とくに、遺産分割協議が長引いていたり、遺産の内容が不透明なまま時間だけが経過してしまうケースでは注意が必要です。
放棄を口頭で家族に伝えていたとしても、家庭裁判所への正式な申述がされていなければ法的効力は一切ありません。手続きを怠ったことで、多額の負債まで相続してしまうリスクもあります。
戸籍の不備で手続きが遅延
必要な戸籍がそろわない場合、相続における名義変更や申告手続きがスムーズに進まず、手続きが長期化する場合があります。被相続人が、結婚や離婚、養子縁組などの戸籍上の異動が多かったりする場合は、速やかに確認する必要があります。
確認資料を取得するまでに1~2週間以上かかることがあり、状況によっては1か月程度要することもあります。こうした事態を避けるためには、相続開始が判明した段階で速やかに戸籍の収集を始めることが重要です。
早めに準備を進めることで、名義変更や税務申告のスケジュールに余裕を持って対応することができ、結果として遅延やトラブルのリスクを最小限に抑えることができます。
相続開始日を正確に把握するために意識すべきこと

相続開始日を正しく理解し、必要な準備をすることで、手続きの遅延やトラブルを防ぐことができます。戸籍の取得や専門家への相談は、早めに行うことが重要です。
早めの戸籍取り寄せが基本
相続人を確認するには、戸籍の取得が望ましいです。相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍をすべてそろえると、ミスなく手続きを進められます。相続人の有無や続柄を明らかにするうえでも重要です。
戸籍の取得には複数の市区町村に請求するケースがあり、時間と手間がかかることがあります。とくに被相続人が転籍を繰り返している場合は、戸籍の数も増える傾向にあります。
戸籍の資料を集めるのは、相続手続きを円滑に進めるために重要であり、その他の書類手続きにも大きく影響します。できるだけ早い段階で必要な戸籍の取得を開始するようにしましょう。
不明な場合は行政書士や司法書士へ相談
戸籍の読み解きが難しい、転籍先が不明など事情がある場合は、専門家に依頼するのが安心です。行政書士や司法書士は、戸籍収集の代行だけでなく、相続関係説明図の作成や手続きスケジュールの管理も含めたサポートを提供してくれることがあります。
期限に追われる中で誤った判断を避けるためにも、専門家の助言は非常に有効です。時間と労力を節約し、スムーズな相続手続きの実現のためにも、早めの相談をおすすめします。
家族間での認識合わせも重要
相続人全員が死亡日や各種手続きの期限について正しい認識を持つことが、トラブルを未然に防ぐ重要なポイントです。相続開始日に対する理解が曖昧なままでは、期限切れによる権利喪失や申告漏れといった問題が発生するリスクがあります。
相続放棄や相続税の申告といった期限が決まっている手続きでは、「聞いたつもり」「話したつもり」といった情報共有の不備が致命的となります。
そのため、家族全員でスケジュールを共有し、必要に応じて専門家を交えた家族会議を開くことが有効です。認識のズレがトラブルにならないように、こまめな情報共有を心がけましょう。
不動産の売却・リフォームのことなら大希企画株式会社に相談!
大希企画株式会社は、1988年創業の地域密着型不動産会社です。不動産の売却、リフォーム、空き家活用など、相続後の物件に関するあらゆる相談に対応しています。
- 累計20,000件以上のリフォーム実績
- 相続不動産の売却戦略や査定も対応
- 空き家プロジェクトを通じた取り組み
「相続した不動産をどうすればいいか分からない」という方は、まずは相談をご活用ください。あなた自身にあう、よりよい不動産の活用方法をみつけましょう。
大希企画株式会社の詳細は、こちらをご確認ください。
まとめ
相続開始日は、すべての手続きや期限の起点となる非常に重要な情報です。死亡診断書や戸籍を確認し、きちんと管理することがトラブル防止につながります。家族や専門家と連携して、相続の手続きを進めることが重要です。早めの準備と相談で、相続の負担を最小限に抑えましょう。
この記事の著者
-

-
運営スタッフ
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。
一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。